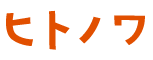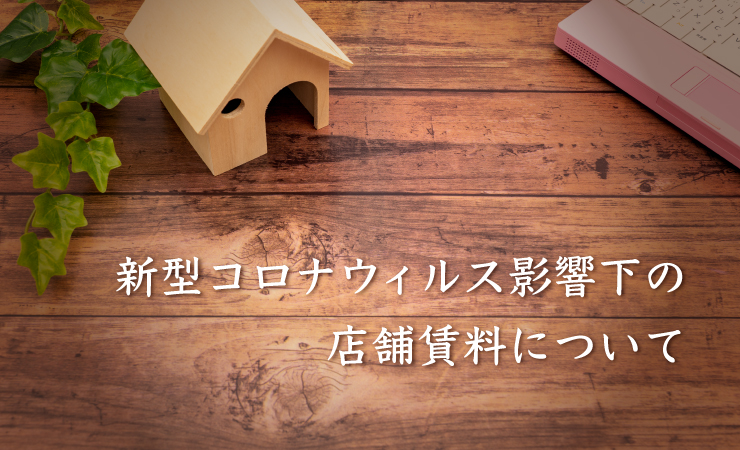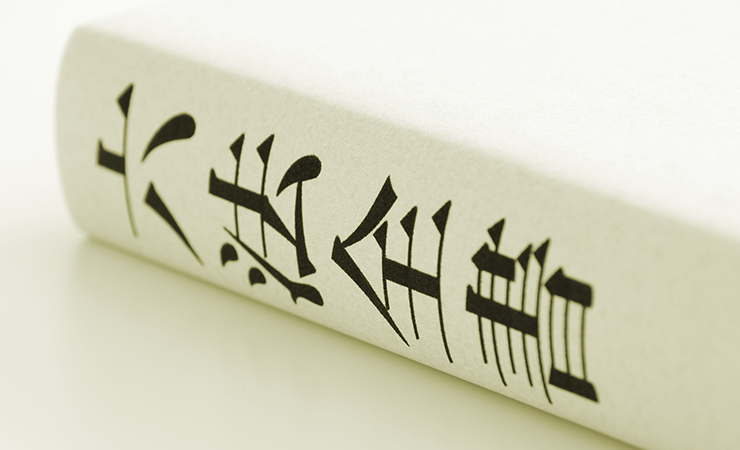皆様、いかがお過ごしでしょうか。弁護士の本多芳樹です。
最近都内ではまたコロナの感染者増えてきましたね。なかなか不安な生活が続きますが、今回はコロナ禍で実際体験された方も多いと思われるテレワークについて考えてみたいと思います。
目次
そもそもテレワークって何?
現在でも在宅勤務している方はたくさんいらっしゃると思いますが、そもそも、テレワークって何かというと、「ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」(総務省ホームページ)です。
本来は政府の働き方改革の推奨としてテレワークが挙げられていましたが、皮肉にもコロナ禍で急速に広がっていきましたね。定義からすると、時間と場所の柔軟性をはかれる働き方のような印象がありますが、ICTを用いて就労「場所」をオフィス(事業所)以外とすることに本質があり、時間の柔軟性は副次的に高まることが期待できるにすぎない制度です。フレックスタイム制、裁量労働制、高度プロフェッショナル制などでも時間の柔軟性は実現可能だからです。
テレワークの契約形態による区分
テレワークにも、雇用型テレワーク(雇用契約を主とする労働契約関係にある労働者が行うテレワーク)と自営型テレワーク(請負・準委任⦅業務委託⦆契約を主とする労働契約関係以外により行うテレワーク)があり、前者は通常勤務と同様に労働時間の規制(一日8時間、週40時間、労働基準法)を受けますが、後者は労働契約ではないので、労働時間規制の制約を受けないという違いがあります。
就労場所による区分
働く場所によっても、テレワークは区分されます。在宅ワーク(自宅で業務を行う形態)、サテライトオフィスワーク(当該労働者の属するメインのオフィス以外のサテライトオフィスや、社外のワーキングスペースなどで業務を行う形態)、モバイルワーク(移動中の駅や空港、顧客先、カフェなど、臨機応変に選択した場所で業務を行う形態)という形態があり、サテライトオフィス勤務以外は雇用型、自営型どちらのテレワークでもありうる形態です。
時間割合による区分
時間割合によっても、テレワークは区分されます。フルタイムでのテレワーク(原則として一切出社しない形態。元々は自営型を想定していたが、現在のコロナ禍では雇用型も多数あり)、と業務の一部のテレワーク化(業務の一部や、一日の労働時間の一部をテレワークとするもの。雇用型を原則として想定。例:特定のデータ入力業務のみテレワークを認める、待ち時間等のモバイルワークを認める、試験的に業務の一部をテレワーク化するなど)があります。
勤務形態選択権の所在
勤務形態を選択できるかということも問題になります。雇用型では、原則として使用者の指揮命令下にあるため、テレワーカーに選択権があることは例外ですので、テレワークを労働者の方から求めることは原則としてできません。逆に、自営型では、使用者という概念がないのでテレワーカーに選択権があるのが原則です。
テレワーク導入のメリット
テレワークを導入することのメリットとしては、企業、就業者、社会それぞれにメリットがあると考えられます。
企業のメリット
- 生産性の向上(業務効率)
- 優秀な人材の確保、離職防止
- コストの削減(通勤費、賃料等)
- 事業継続性の確保(大災害が起こった場合でも事業がストップしない体制を整えられる、等)
就業者のメリット
- 多様で柔軟な働き方の実現
- 仕事と育児、介護、治療の両立
- 通勤時間の削減
社会全体のメリット
- 労働力人口の確保
- 地域活性化(働く場所を選べないため東京一極集中化をさけ、サテライトオフィスを地方に作ればその周辺地域の経済が活性化する、等)
テレワーク導入のデメリット
テレワークを導入することのデメリットとしては、
- 仕事と私生活の区別が曖昧となることによる弊害(残業が増える、労働時間の管理が難しくなる、等)
- 出社しないこと自体による業務効率の低下(仕事と私生活の気持ちの切り替え方が難しい、等)
- セキュリティ上の懸念(機密情報の漏えい防止、等)
- コストの増大(情報通信機器の購入費、通信費の増大、等)
- 組織としての一体感低下のおそれ(直接顔を合わせてコミュニケーションをとらないので、コミュニケーション不足により組織としての一体感が醸成されにくい、等)
- 不公平感助長のおそれ(特定の者のみにテレワークを命じた場合、テレワーカーと通常勤務者の賃金に差を設けた場合、等)
- 同一労働同一賃金の問題(正社員とパート労働者とで同じテレワークをさせた場合に賃金に差が生じるような場合、等)
もっとも、コロナ禍では、デメリットがあるからテレワークを導入しないということは難しいので、デメリットをどのように減らしてテレワークを導入していくのかというのが課題になってくると思います。例えば、コストの増大については、テレワーク助成金である程度解決できます。
テレワーク導入にあたっての留意点
雇用型のテレワークを前提として述べますが、テレワークを導入するにあたっては、①新規採用者に労働契約時に就業場所としてテレワークを行う場所を明示すること、労働者に選択権を与える場合には、テレワーク可能な場所や条件を明示することが必要になります。また、②通信費用を労働者に負担させる場合等、テレワーク特有の問題が生じる場合には、就業規則の変更が必要になる場合があります。
そして、就業規則でテレワークについて定める場合には、
- 目的・適用範囲
- 定義規定
- テレワーク就業許可基準に関する規定
- 服務規律に関する定め
- 労働時間に関する定め
- 給与・手当に関する定め
- 業務遂行方法に関連する規定
等を定めておいた方がよいです。
興味ある方は、厚労省テレワークモデル就業規則、作成の手引きというのが公開されているので、参照してみてください。
さいごに
コロナ禍で出社できないためやむを得ずテレワーク導入したという所が大部分だと思いますが、テレワークとは何か、メリット・デメリット、導入にあたっての留意点等を考えてみるのも、使用者・労働者双方にとって有意義だと思って今回はテーマに選んでみました。
それでは、また次回もよろしくお願いいたします。
テレワーク導入のご相談はこちら
二子玉川総合法律事務所
東京都世田谷区玉川1-9-20スタンダビル1階
TEL:03-5797-9572(直通) 03-5797-9531(代表)
E-mail:y.honda@nikotama-law.com
この記事を書いた人

本多 芳樹(ほんだ よしき)
埼玉県出身。現在東京都在住。弁護士歴12年。
労働問題を専門とする弁護士事務所で長年勤務した後、2年前に独立。現在は労働問題を中心に民事事件全般を手掛けている。趣味は、フットサル。最近の趣味は、ゴルフのコースデビューを目指して、レッスンで練習中。